こんばんは、ミントです。
なんとなーく国税徴収法の勉強を始めて、早1か月。
「3歩進んで2歩戻る勉強法」により、国税徴収法の計算テキストが、もう少しで最後のページまで辿り着きそうです。
【関連記事】国税徴収法2022年用の理論マスターを買ってみた
2019年度に大原の通信(時間の達人)で国税徴収法を勉強していたんですけど、その時に計算テキストの後半部分って理解不能な部分が多かったんですよね。
特に嫌いだったのが根抵当権。
「優先額の限度等」が本当に分かりませんでした。
極度額、配当時債権額、差押通知時債権額、などなど、同じ抵当権でも色々な種類の金額がでてきて、どれとどれがどうなっているのやら・・・と頭がこんがらがっていたんですけど、なんてことはない。
計算テキストを自分で隅から隅まで読んでいたら意味が分かりました。
分かると意外と単純で、パズルみたいですね。
国税徴収法上の優先権と、民法上の優先権の考え方が違うけど、国税が絡んだら「国税徴収法」、絡まなかったら「民法」って考えれば、あぁそうかそうか、と。
勉強は分かってくると楽しい。
2018年に合格した消費税法の勉強の時も感じたけど、「計算テキスト」って案外侮れないんですよね。
理論の理解の手助けになることも多いし、規定の趣旨なんかは「理論テキスト」よりも「計算テキスト」の方がシレッと分かりやすく書かれたりしているし(大原の場合)。
国税区徴収法の場合、計算は殆どでないらしいから「計算テキスト」をどれくらいの精度で読み込む必要があるのかはイマイチ不明ではあるけれど、「計算テキスト」も繰り返し読んでいこうと考え中。
理論暗記が苦手な私には、理論だけ勉強するのはキツいのです。
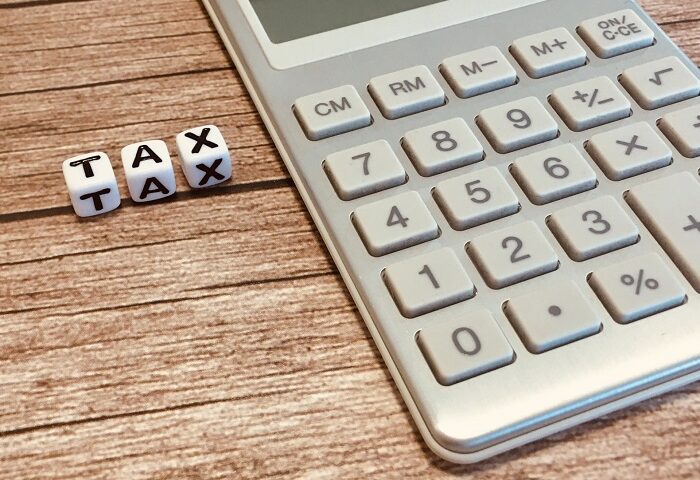
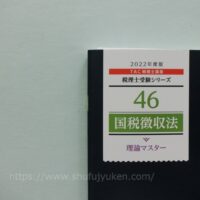


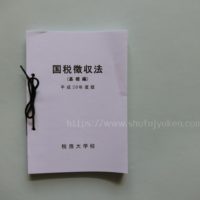



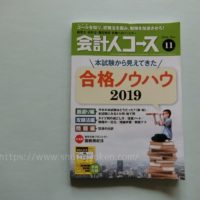




この記事へのコメントはありません。